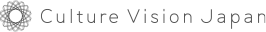「時を超える:美の基準」展開催レポート

二条城二の丸御殿台所の前の庭から見る、名和晃平《Tornscape》(2019)
古きものと新しきものが共生する街で
「千年の古都」と呼ばれるにふさわしい情緒と空気に包まれた街・京都は、ある意味、日本でもっとも新鮮でヒップな街になりつつあるのではないでしょうか? 年々外国人観光客の数は増加し、その顔ぶれも欧米、中国、東南アジア……と多彩で、まるで多国籍都市の様相を垣間見せています。それに並走するかのように、若い世代が立ち上げたバル、カフェ、アートをテーマにしたショップやホテルが小さな路地のあちこちに顔を覗かせ、伝統的な都市の景観のなかでみずみずしく産声をあげています。クラシックとコンテンポラリーが共生し、温故知新を体現するのが今日の京都なのです。さらに今年2019年9月初旬には、日本初開催となるICOM(国際博物館会議)大会が開催され、世界中の美術館・博物館の学芸員、キュレーター、研究者が一堂に会し、芸術文化の未来を議論し、交流を行う約1週間のきわめて重要な会合も行われました。その意味でも、京都にはかつていない国際的な注目が全世界から注がれた、と言えるでしょう。
そんな晩夏の時期に開催されたのが「時を超える:美の基準 Throughout Time: The Sense of Beauty」展。カルチャー・ヴィジョン・ジャパンが細見美術館、京都市、京都市教育委員会、京都市内博物館施設連絡協議会とつくる実行委員会で主催いたしました。
会場は京都中心部に広がり、大政奉還などの歴史的大イベントの場となった元離宮・二条城(重要文化財)。その重厚な内部に、最先端の現代美術、それも日本を代表するアーティストたちの作品がずらりと並ぶのだから見逃す手はありません。わずか4日間の会期にも関わらず5000人を超える来場者が訪れた同イベントをレポートします。
座って見る、現代美術
全6棟からなる二の丸御殿に隣接する台所(と言っても、その大きさは並みのキッチンとは比べものにならないくらい圧倒的に広い)と御清所の2か所を展示会場とした「時を超える〜」展の展示キュレーションを担当したのは、森美術館の館長を長年務め、国際的な展覧会の企画も数多く手掛けてきた南條史生氏と、京都を拠点に国際的な活動を行う彫刻家の名和晃平氏。2人は「歴史との対話」をテーマに、日本の美学とは何か? 何が新しく普遍的なのか? 古いことと新しいことの価値は何か? といった問いを今展に込めたといいます。
その狙いを明確に伝えているのが、まずはその独特の展示構成です。通常、現代美術の展示空間というとホワイトキューブと呼ばれる均質な空間を、歩いたり立ち止まったりする鑑賞形式がスタンダード。ですが、この展覧会では鑑賞者が自ずと床に座り、作品と対面するような設えが随所にあります。例えば京都画壇を代表する伊藤若冲の《鶏図押絵屏風》の高精細レプリカと、京友禅と日本画の工房などが共同で立ち上げたチーム「RINne Associe」による、インターネット上の歌姫ことヴォーカロイド初音ミクと若冲画の鶏が描画された掛け軸の並ぶスペースでは、偶然にも両作ともが鑑賞者が座ったときの目の高さに合わせて配置されています。 かつて二条城で暮らし働いていた人々の視線と同じ場所に、 江戸と現代のアイコニックなイメージが設えるという、遠い2つの時代を結ぶユーモアが心憎い。そして、この日本的な空間は次なるスペースへの導きともなっています。

展示風景。右は1797年作の伊藤若冲《鶏図押絵貼屏風》(細見美術館蔵)の高精細複製、左はRINne Associe《初音ミク×伊藤若冲》(2017)

RINne Associe《初音ミク×伊藤若冲》(2017)
二条城の美しい庭園が眺められる畳敷きの御清所に並ぶのは、青木美歌によるガラス作品《煙庭》。かつて囲炉裏として使われていたとされる場所の上に、煙や気体、微生物の分子構造を思わせる透明で繊細なガラスのオブジェがいくつも並び、プリミティブでささやかな美のあり方を示しています。
そしてその奥には、小林且典が山の稜線を模して鋳造したブロンズ《山の標本》がひそやかに配されています。手前に両手に乗るほどの「山」、その後景にはリアルな庭園が広がって、遠近感がしばし惑わされます。このちょっとした箱庭的世界は、日本の文人たちが愛した盆栽や庭の歓びを思い起こさせるでしょう。
さて、ここにはもう一つ、白石由子による《蜘蛛の糸、鏡ばりの部屋》という作品があるはずですが、見当たりません。しばし迷って、そして気づいたのが「音」でした。由子の母である詩人・白石かずこが2005年に書いた二条城についての詩と、ドビュッシーなどの楽曲を組み合わせた音の風景は、日本建築の空間を自由に浮遊し、鑑賞者の耳に届けられます。二条城の歴史を音で触れるような清涼な経験が楽しく感じられます。

青木美歌《煙庭》(2019)

小林且典《山の標本》(2019)
更新される日本的なる美
御清所には、これら以外にも向山喜章による絵画《ヴェンダータ》シリーズが壁ではなく畳の上に配置されたり、西川勝人による細長いらせん形のブロンズ《Courant ascendant Ⅰ》が薄闇のなかに直立して置かれていたりします。西洋的なペインティングや立像のフォルムや視覚的要素を、日本的な美学によって読み替え設え直す意欲的な実験と言えるでしょう。
そしてその隣には、チームラボによる映像作品《生命は生命の力で生きている》。宙に浮かび、ゆっくりと回転するCGの古木は角度によっては「生」の文字に見えます。そこに次第に萌してくるのは花々や苔や小鳥たち。先端的な映像技術によって表現された動的な生命のあり方は、長い時間を生きてきた二条城の歴史そのものの凝集した姿のようにも見えます。生々流転する自然と時間のなかで育まれてきた美意識が、新しい技術によってよりクリアーに見えてくるのです。

向山喜章《ヴェンダータ53 – 薫風/くんぷう》(2018)

西川勝人《Courant ascendant I》(1995)

チームラボ《生命は生命の力で生きている》(2011)
御清所を後にし、台所のスペースへと戻ります。その奥に展示されているのが、須田悦弘の《露草》とミヤケマイの《誰が袖》だ。前者は極めて精緻な木彫の技術でつくった原寸大の露草の花。本物と見紛うばかりの彫刻が、竹製の結界にそっと置かれています。気付かなければ通り過ぎてしまうほどの小さな美。そして後者は、伝統的な「誰が袖屏風」の様式から着想したインスタレーションです。場所の記憶に寄り添ってうつわや古道具を用い、まるで神に供物を捧げる神饌(しんせん)のような設えに、凛とした気持ちが呼び起こされます。
繊細なものへと気持ちを集中させる鑑賞のベクトルは、同じく台所に展示された宮永愛子の《夜に降る景色 -時計-》にも通じます。時とともに揮発していくナフタリンを素材にした宮永の彫刻は、その繊細さによって物や事の儚さを伝えてくれます。ささやかな諸行無常。それは江戸幕府の盛衰のみならず、人間の有限な生そのものをも象徴するかのようです。

須田悦弘《露草》(2019)

ミヤケマイ《誰が袖》(2017)

宮永愛子《夜に降る景色 -時計-》(2018)
無常でつながる過去と現在
これでほとんどの作品を見て回ったことになりますが、じつを言うと、ここまで紹介してきた順番は、本来の順路を逆走するような並びなのです。鑑賞者が台所に入った瞬間に目に飛び込んでくる「出会い」の作品を最後に紹介したいと思ったのは、同作が今展にとってとても重要であると感じるから。名和晃平の新作《Tornscape》です。

名和晃平+白木良(プログラム)+原摩利彦(サウンドスケープ)
《Tornscape》(2019)
プログラマーの白木良と音楽家の原摩利彦と共作したこの巨大な映像作品は、鴨長明の『方丈記』をモチーフに、現在世界的に緊迫した議論の進む気候変動や天災のアルゴリズムを自動生成する、そのつど生まれては消えていくリアルタイムの映像インスタレーションなのだといいます。中世期に記された『方丈記』は、晩年を迎えた長明が小さな庵で記した随筆で、当時の生活や天災について記述されています。鎌倉時代の京都に生まれた歌人が見た風景と、現代のアーティストたちが情報技術の力を借りて現出させた現代の風景。その共鳴を、映像はひび割れた氷や泡のようなイメージとして鑑賞者に示します。それはまるで「無常」によって結ばれた時間旅行のようでもありました。そしてその横には、この展示全体の守り神のような、名和晃平の鹿をかたどった作品《PixCell-Deer#60》が静かに佇んでいました。

名和晃平《PixCell-Deer#60》(2019)